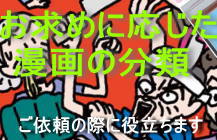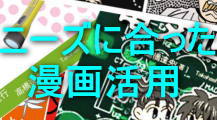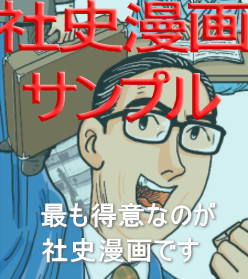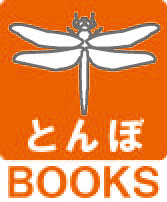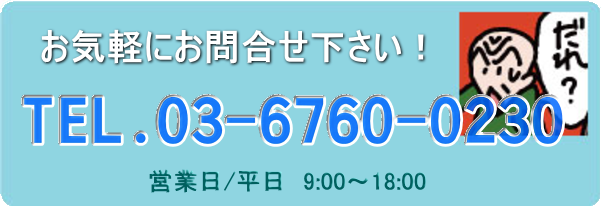���搧��Ŏg����ƊE�p���m���Ă����Ɖ����ƕ֗��ł��B
| HOME�� ���搧��Ŏg����p��̐��������s�����t |
 |
| ����𐧍삵�������܂ŁA�ƊE�Ŏg������p��̒m���͕K�{�ł��B�ł����킹�̒i�K���犮���܂ŁA���p��͕p�ɂɎg���܂��B���������p����ڂ�������������܂��B ���Ђ��𗧂ĉ������B |
| ���t |
| ���� |
| 1.���t�Ƃ� 2.���܂����`���͂Ȃ� 3.���t�̗��j 4.��g���X�̉��t |
| �����t�Ƃ� �P�s�{�Ȃǂ̏��Ђ̖{�����I�������⊪���ɁA���҂̏��⏑�ЂɊւ��鎖���Ȃǂ��L�q����Ă��܂��B������u���t�v�Ƃ����܂��B �������A���{�̏��Ђɂ́u���t�v��t����̂���ʓI�ł����A�m���ɂ͂��̏K���͂���܂���B���Ȃ݂ɁA�m���̏ꍇ���g�r���ɕW��⒘�Җ��A�o�ŎЖ��Ȃǂ��L���Ă���܂��B ���ڂɖ߂� �����܂����`���͂Ȃ� �u���t�v�ɂ͌��܂����`��������܂���B�����̒����̏ꍇ�A�u���t�v�ɂ́u�o�ŔN�����v�u���Җ��v�u�o�ŎЖ��ƏZ���v�u�����Ж��ƏZ���v�ȂƂ��L���Ă���܂��B�܂��A���҂Ɋւ�����⏑�ЂɊւ��郁�b�Z�[�W�Ȃǂ��L���Ă���܂��B ����ɁA�{���������łȂ̂������Ȃ̂���������悤�ɂ��Ă��܂��B���Ƃ��A�u2025�N10��10����1�����s�v�Ƃ��u2026�N2��1����2�����s�v�ȂǂƋL����܂��B ���ڂɖ߂� �����t�̗��j �u���t�v�̗��j�͌Â��A�]�ˎ���ɑk��܂��B1722�i����7�j�N1���̑剪�����ɂ��u�V�쏑�Џo�V�V�ɕt�G���v�ɗR�����Ă��܂��B�剪�����̓e���r�ł�����݂̍]�˓쒬��s�ł��B �����A�C���ł̏��Ђ����s���Ă����̂�剪�������뜜���āA�Ō����X�̏o�Ō��m�ɂ����̂ł��B�������A�Ŗ������Đ��{���Ă����̂ł����A�u�Łv�Ɓu����v�����m�ł͂���܂���ł����B����ɔŖ����Ă����悤�ŁA�Ō����s�m���ȏ�Ԃł����B ���ڂɖ߂� ����g���X�̉��t �₪�Ė�������ɂȂ�ƁA�o�Ŗ@�ɂ���ď��Ђ̔��s�Җ��ƏZ���A�o�ł̔N�����A������̖��̂ƏZ���Ȃǂ̋L�ڂ��`���t�����܂����B��������ɂ́A��g���X���قڌ��݂̂悤�Ȍ`�Łu���t�v���L�ڂ���悤�ɂȂ�܂����B �������A��ʏ��ЂɊւ��ẮA���݁u���t�v�̋L�ڋ`���͂���܂���B�u���t�v��t���Ȃ��Ă��o�ł͉\�Ȃ̂ł��B����ł��A�قƂ�ǂ̎s�̂���Ă����ʏ��Ђɂ́u���t�v���L���Ă���܂��B����͊��K�ƂȂ��Ă��邩��ł��B�������A�����Ȋw�Ȃ̌���������ȗp�}���ɂ͋L�ڋ`��������܂��B ���ڂɖ߂� |
| �Q�l�y�[�W�� �v���b�g ���m���[�O ���炷�� ���[�h �r�� �C���g���_�N�V���� ���n�� ���t ���� �Q�l���� |
| ���s�@���s�@���s�@���s�@�ȍs �͍s�@�܍s�@��s�@��s�@��s |
 takataka1123@office.nethome.ne.jp |





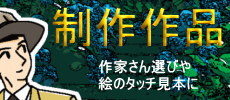
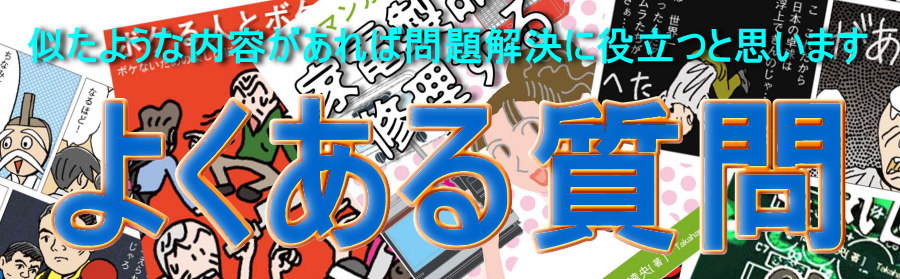


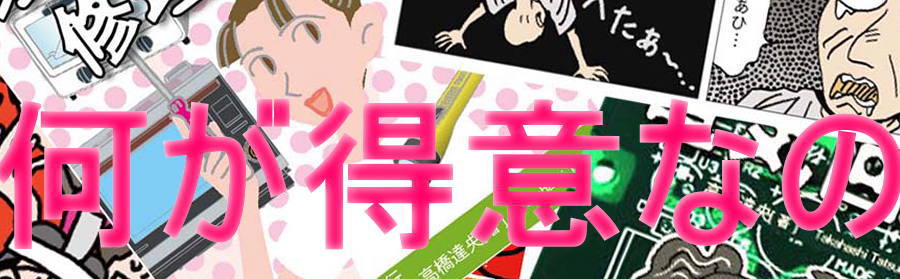


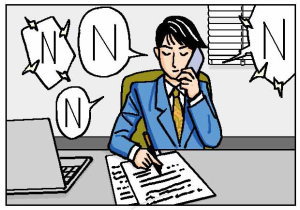 �A�q�A�����O
�A�q�A�����O �C���t����
�C���t���� �E�l���̃y������
�E�l���̃y������ �F�w�i�������
�F�w�i�������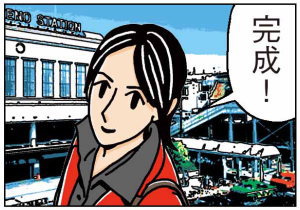 �G����
�G����